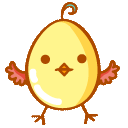
[東京 22日 ロイター] - ブロックチェーン技術(分散台帳技術)を応用すれば、デジタル通貨にマイナス金利やプラスの金利を付与することができ、現在の金融政策よりもダイレクトに効果が出る──。
中島真志・麗澤大学教授は、金融政策に新たな政策手段を加えることが可能との見方を示す。ただ、実現するまでには数多くのハードルをクリアする必要がありそうだ。
中島教授は、日銀に在籍し金融研究所に勤務していた際に、1990年ごろから始まった「電子現金プロジェクト」と呼ばれていたデジタル通貨の研究に携わった経験もあり、資金決済やそのシステムに詳しい。
中島教授によると、中央銀行がデジタル通貨を発行し、銀行券のように広く利用されるになると、デジタル通貨自体にマイナス金利やプラス金利を自由に付けることによって、電子台帳上でデジタル通貨の残高を減額あるいは増額できるようになる。
具体的には「デジタル通貨が銀行券のように広く普及した世界においては、金融緩和による金利引き下げの代わりに、中央銀行が台帳の残高を一定期間ごとに一律に減らしていけば、電子的な形で、マイナス金利を付けることができる」と説明。
「1000円が1年後に990円に減るようにすれば、1%のマイナス金利を実現できる。そうすれば人々はなるべく早く通貨を使うようになり、消費や投資が刺激され、景気が上向くことが期待できる」と解説する。
逆に「プラス金利の場合は台帳上の残高が増えていくことになり、景気過熱が抑制されることになる」と話し、現行の金融機関を仲介した金融政策よりも、緩和や引き締めの効果が強くなるとみている。
すでにイングランド銀行の論文では、デジタル通貨を「第2の金融政策手段」と呼んでおり、景気変動に対する機能が大幅に強化されると予想しているという。
<必要な取り付け防止策>
一方で、中銀デジタル通貨が、金融不安定化につながる面も指摘している。デジタル通貨と銀行券が併存しているケースでは、例えばマイナス金利のデジタル通貨から金利ゼロの現金へのシフトが発生したり、逆にデジタル通貨の金利が高ければ、預金から大量の資金が流失し、「取り付け騒ぎ」が起きかねないリスクもある。
銀行経営が全般に不安定化している環境下で、このような資金シフトが発生すると、現在よりも数段速いテンポで資金が流出し、結果的に金融不安を増幅させる効果が出ることも予想されるという。
中島教授は「デジタル通貨の発行やそれに対する付利については、このように金融政策面からの検討のみならず、プルーデンス政策の面からの配慮も求められる」と指摘している。
2018年2月22日 / 11:28 / 20時間前更新
ロイター
https://jp.reuters.com/article/blockchain-digital-currency-idJPKCN1G6073
■関連スレ
【スウェーデン】「現金お断り」が当たり前−あまりに急激に進むキャッシュレス化に中央銀行も困惑 公式通貨のデジタル発行を検討
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1519197864/
【仮想通貨】ビットコイン、通貨としておおむね失敗=英中銀総裁 ★4
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1519125942/
【ベネズエラ】 “世界初”国家が発行する仮想通貨「ペトロ」豊富な原油担保に 「1ペトロ」を60ドルから
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1519211990/

